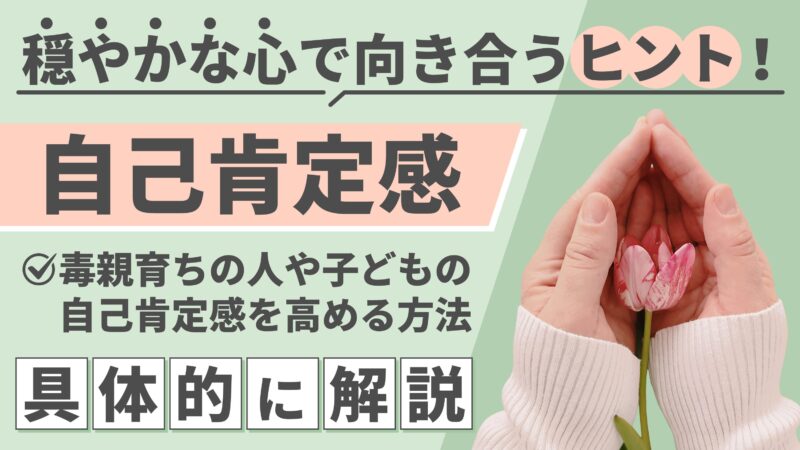
- 自分に自信が持てず生きづらさを感じている
- 毒親と同じように子どもにきつく当たってしまう
- 毒親の連鎖を自分の代で断ち切りたい
毒親の元で育った人は自分が受けた経験を無意識に子どもへ繰り返してしまうことがあります。自分もまた毒親になってしまったと感じ、自己肯定感が低下するかもしれません。
この記事では毒親育ちの人が、自分と子どもの自己肯定感を高める具体的な方法を解説します。この記事を読めば毒親の連鎖を断ち切り、穏やかな心で自分と子どもに向き合うヒントが得られます。
毒親育ちの過去は変えられませんが、自己肯定感は日々の習慣で高めることが可能です。小さな成功体験を積み重ね、自分らしく過ごせる毎日を目指しましょう。
自己肯定感とはありのままの自分を肯定する感覚のこと

自己肯定感とは自分を条件なしに受け入れ、大切に思う感覚のことです。何かができた時だけに感じられるものではなく「自分はこのままでいい」という心の土台があることを自己肯定感と呼びます。
自己肯定感について以下の項目に沿って解説します。
- 自己肯定感と自己効力感の違い
- 自己肯定感が低い人の特徴
- 自己肯定感の低さが生活に及ぼす影響
自己肯定感と自己効力感の違い
自己肯定感と自己効力感はよく似た言葉ですが、意味は全く異なります。それぞれの違いは以下のとおりです。
| 項目 | 自己肯定感 | 自己効力感 |
| 定義 | 「ありのままの自分」を認めること | 「自分にはできる」と信じること |
| 対象 | 存在(Being)への自信 | 行動(Doing)への自信 |
| 特徴 | 成果や達成に関係なく、自分の存在そのものに価値があると感じること | 特定の目標や課題に対して「やり遂げられる」と自分の能力を信じること |
| 具体例 | 「失敗しても自分の価値は変わらない」と思う | 「自分はうまくやれる」と思う |
自己肯定感は心の土台で、自己効力感は行動を起こすためのエネルギーと言えます。
自己肯定感が低い人の特徴
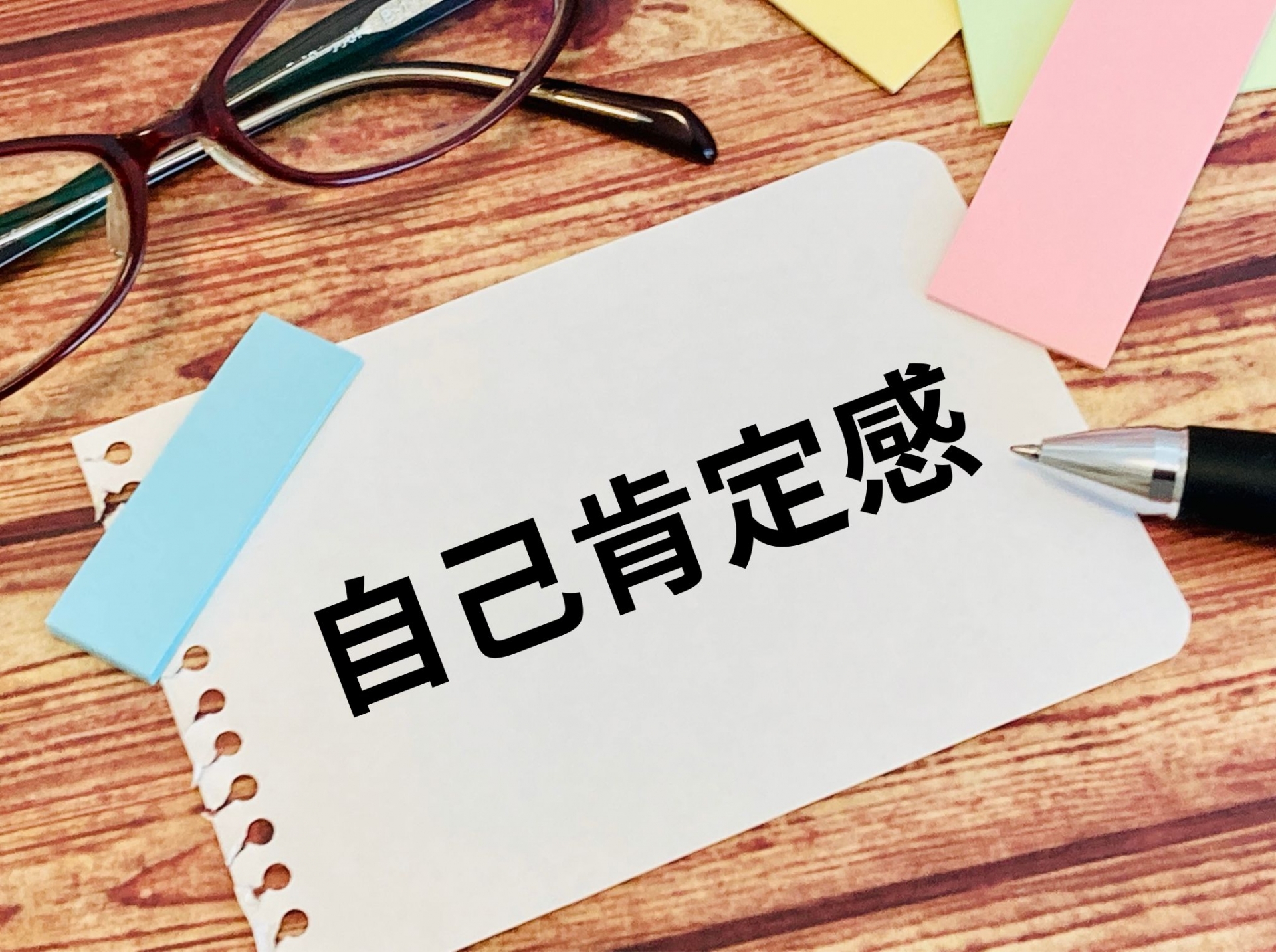
自己肯定感が低い人は自分に自信が持てず、常に他人からの評価を気にしたり、物事を悪い方向に考えたりする傾向があります。自己肯定感が低い人の特徴は以下のとおりです。
- 他人と比べて落ち込む
- 失敗を極端に怖がる
- 自分の意見を言えない
- 褒め言葉を素直に受け取れない
- 「どうせ自分なんて」を言う癖がある
- 何でも自分のせいだと思い込む
- 頼み事を断れない
- すぐに謝る
自己肯定感の低さは思考や行動に表れ、日常生活の質を低下させてしまいます。
»アダルトチルドレンの症状とは?抱えやすい精神疾患と克服方法を解説
自己肯定感の低さが生活に及ぼす影響
自己肯定感が低いと人間関係や仕事、子育てなど日常生活の様々な場面で影響を及ぼすことがあります。自己肯定感の低さが日常生活に及ぼす影響は以下のとおりです。
- 他人の顔色や評価を気にしすぎる
- 他人との比較で劣等感を抱く
- 新しい挑戦への恐怖を感じる
- 恋愛や結婚で依存しやすい
- 子育てに対する思い込みが強くなる
- 精神的な不調が現れる
- 悲観的な思考に陥る
自己肯定感が低いと自分らしく生きられず、日々の充実感を失いやすくなります。
毒親育ちの人が自己肯定感を高める方法9選
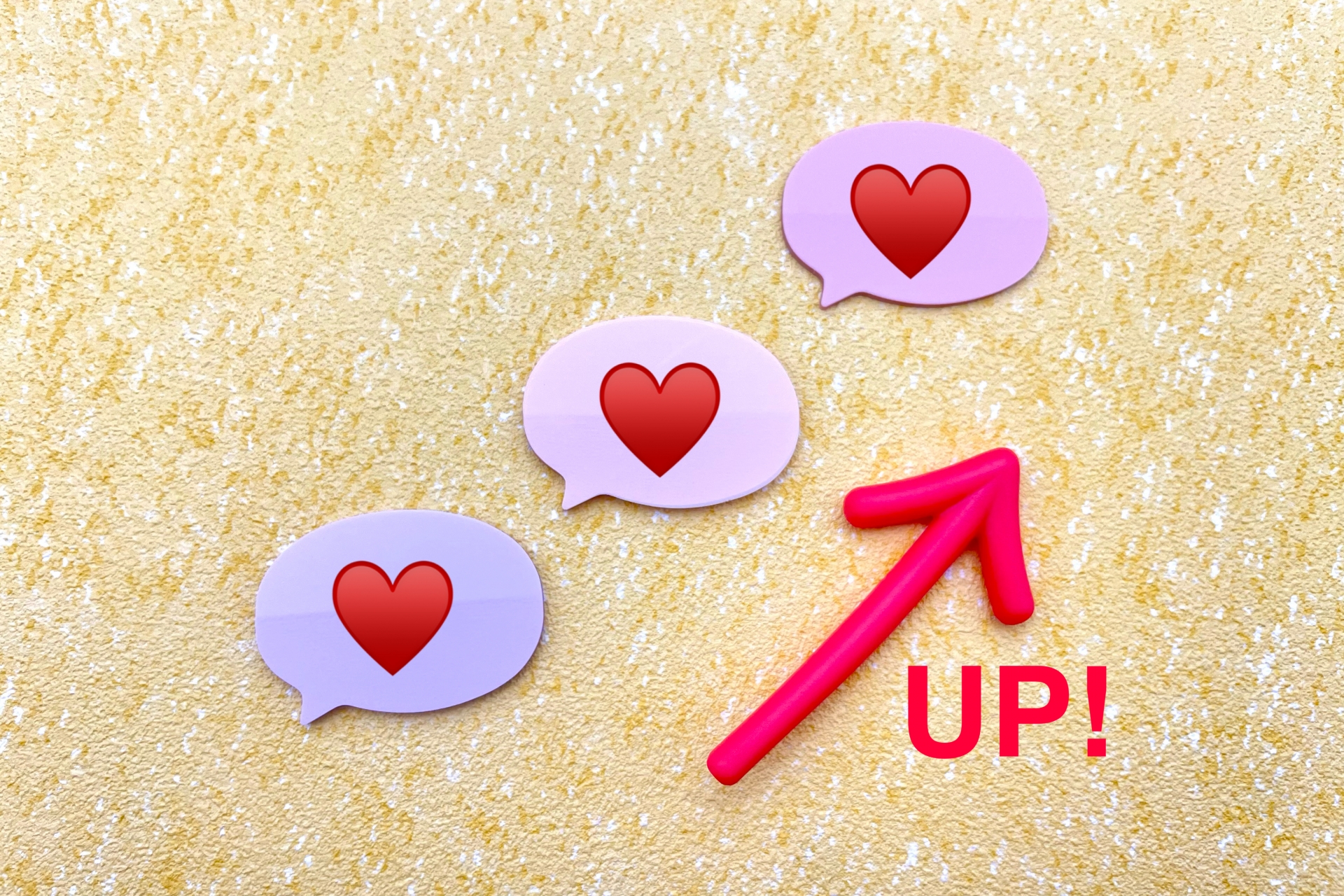
毒親育ちの人でも日々の習慣や考え方を変えることで、自己肯定感を高められます。自己肯定感を高める具体的な方法は以下のとおりです。
- 小さな成功体験を積み重ねる
- ポジティブな自己対話を行う
- 自分を肯定的に捉える習慣を持つ
- 新しい挑戦を楽しむ
- 信頼できる人間関係を築く
- 日記をつける
- フレーミングする
- 感謝の気持ちを持つ
- 健康的なライフスタイルを心掛ける
小さな成功体験を積み重ねる
自己肯定感を高めるためには「自分にもできた」という気持ちを育てられるよう、小さな成功体験を積み重ねていくことが大切です。毒親の影響で「自分には何もできない」と思い込んでいても、成功体験を積み重ねることで少しずつ考え方を変えられます。
成功体験を得るためにはベッドメイクや5分間の散歩、就寝前の水分補給など毎日達成できる簡単な目標から始めてみましょう。目標を達成したら手帳やカレンダーに印をつけるなど、成果を見える形で残すことも自己肯定感を高めるために効果的です。
完璧でなくても「行動できた」という事実を認め、自分を責めないことが自己肯定感につながります。
ポジティブな自己対話を行う

頭の中で自分にかける言葉を意識的に変えると、自己肯定感が高まります。自分を厳しく責めるのではなく、親友を励ますように優しくポジティブな言葉をかけましょう。
毒親の元で育った人は、毒親から言われた否定的な言葉を無意識に自分自身にも繰り返してしまう傾向があります。しかし、自分との対話(自己対話)をポジティブなものに変えるだけで、自分を大切にする感覚を育てられます。
日常生活の中で取り入れられる自己対話の工夫は以下のとおりです。
- ネガティブな口癖を前向きな言葉に言い換える
- 失敗した時に「大丈夫」と自分を慰める
- 否定的な考えを柔らかい表現に変える
- 鏡に映る自分へ励ましの言葉をかける
- 自分自身に感謝の気持ちを伝える
最初は違和感があるかもしれませんが、コツコツ続けることで自己肯定感が高まっていきます。
自分を肯定的に捉える習慣を持つ
自分を肯定的に捉える習慣を日々の生活に取り入れることは、自己肯定感を高めるために欠かせません。毒親に育てられた経験から、無意識に自分を責めたり否定したりする癖がついている人も多くいます。思考の癖を変えるためには、自分を肯定する行動を習慣化することが有効です。
自分を肯定的に捉えるための工夫は以下のとおりです。
- 自分の良いところを書き出す
- ネガティブな口癖を前向きに言い換える
- 完璧を目指さず「できたこと」に目を向ける
- 小さなことでも自分を褒める
- 湧き上がる感情をそのまま受け入れる
自分を肯定的に捉える行動を積み重ねていくことで、自分に対する見方が少しずつ変わり、自己肯定感が高まります。
新しい挑戦を楽しむ

新しく挑戦することは自己肯定感を高めるうえで有効な方法です。毒親に育てられた経験から失敗を過度に恐れる人は多いですが「挑戦できた」という事実が自信につながります。
新しい挑戦を楽しむためには大きな目標を立てる必要はありません。完璧を目指さず「まずは試してみよう」という気持ちで始めてみましょう。いつもと違う道を歩くことや、1人で楽しめる趣味に取り組むことも新しい挑戦の一つです。子どもの頃に好きだったことをやってみるだけでも、自己肯定感を高めるきっかけになります。
新しい挑戦をするうえで大切なことは結果ではなく「行動できた自分」を褒めることです。失敗しても「学びの機会」や「新しい発見」として捉え直しましょう。
信頼できる人間関係を築く
ありのままの自分を受け入れてもらえる相手と信頼できる人間関係を築くことは、自己肯定感を高めるために欠かせません。毒親との関係で傷ついた経験があると人との健全な距離感がわからず、人間関係に悩むことがあります。信頼できる人間関係を築くための工夫は以下のとおりです。
- 否定せずに話を聞いてくれる人を大切にする
- 傷つける言動をする人とは距離を取る
- 安心できる相手に相談する
- 無理な頼みは断る習慣をつける
- 小さなことから助けを求める練習をする
人に頼ることが苦手な場合は「小さなお願い」から始めてみると、信頼関係を築くきっかけになります。大切なことは一方が頼りすぎるのではなく、お互いに支え合える関係を意識することです。安心できる人と過ごすことで、自分を大切にする感覚は育まれます。
日記をつける

日記をつけることは自分の心と向き合い、自己肯定感を高めるうえで大いに役立ちます。頭の中で繰り返される毒親への怒りや悲しみ、自責の念を紙に書き出すことで、思考と感情を整理できるためです。
日記を書く際に完璧を目指さず、ありのままの自分を表現することが自己肯定感を育む一歩です。以下の内容を意識し、まずは1行から日記を始めてみましょう。
- ネガティブな気持ちをそのまま吐き出す
- できたこと・嬉しかったことを記録する
- 自分を褒める言葉を書き留める
- 「〜すべき」という思考を問い直す
- 事実と感情を分けて書く
誰にも見せない日記であれば安心して本音を書けます。日記を続けることで自分を大切にする感覚が少しずつ育ち、自己肯定感は高まっていきます。
フレーミングする
出来事や自分の短所の捉え方を別の角度から見直す「フレーミング」という方法は、自己肯定感を高めるうえで効果的です。物事の捉え方を少し変えるだけで、気持ちが前向きになります。
毒親育ちの人は毒親から言われたつらい言葉や過去の経験が、無意識のうちに自分を責める考え方につながっている場合があります。フレーミングは自身の否定的な考え方の癖を、意識的に肯定的に変えていくことが可能です。
フレーミングの例は以下のとおりです。
| 対象 | ネガティブな捉え方 | フレーミング後の捉え方 |
| ネガティブな出来事 | 仕事で失敗した | 成長するための良い経験ができた |
| ネガティブな出来事 | 人から批判された | 自分にはなかった新しい考え方を知れた |
| 自分の短所 | 心配性でいつも不安 | 慎重に物事を考えられる |
| 自分の短所 | 頑固で人の意見を聞かない | 自分の意志がしっかりしている |
過去に毒親から言われた言葉には「毒親自身の不安や考え方の表れで自分の価値とは関係ない」と客観的に捉え直してみましょう。物事を見る枠組み(フレーム)を意識的に変える習慣を持つことで、否定的な感情に振り回されにくくなります。
感謝の気持ちを持つ

感謝の気持ちは物事を肯定的に捉えることにつながります。日常の中に小さな幸せを見出せるようになるとネガティブな思考に振り回されにくくなり、自己肯定感の向上にもつながります。
- 感謝したことを3つ書き出す
- 1日の終わりに「よかったこと」を書き出す
- 誰かに「ありがとう」と伝えたことを記録する
- 自分に向けて「今日もよくやった」と書き残す
感謝の気持ちを持ち続けることで心が満たされ「自分はここにいていい」と思える感覚が育まれます。
» 親に感謝できない理由と自分の気持ちと向き合う3つのステップ
健康的なライフスタイルを心掛ける
心と体は密接につながっているため、健康的なライフスタイルを心掛けることは自己肯定感を高めるうえで欠かせません。体調が優れないと心も不安定になり、ネガティブな感情やイライラを引き起こしやすくなります。しかし、体が元気だと心も前向きになり、物事をポジティブに捉えやすくなります。
健康的なライフスタイルを送るために、日常生活の中で以下の習慣を意識してみましょう。
- 栄養バランスの良い食事をとる
- 軽く体を動かす(ウォーキングやストレッチなど)
- 7時間以上の睡眠を確保する
- 朝の光を浴びる
- 意識的にリラックスする時間を持つ
体をいたわることは自分を大切にする行動そのものであり、自己肯定感を育てる土台となります。
毒親育ちの人が子どもの自己肯定感を高める方法4選

毒親育ちでも子育てに不安を感じる必要はありません。子どもの自己肯定感は以下の方法を取り入れることで自然に育まれていきます。
- 子どもの感情を受け入れて認める
- 努力や結果を褒める
- 他の子どもと比較しない
- 失敗を成長の一部として捉える
子どもの感情を受け入れて認める
子どもの自己肯定感を高めるには子どもが安心感を抱けるように、感情をありのまま受け入れて認めることが大切です。子どもが示す喜びや怒り、悲しみといった気持ちに「良い・悪い」の判断をしないようにします。
子どもが泣いている時は「そんなことで泣かないの」と否定せず、最後まで話を聞きましょう。子どもの気持ちに共感し、背景にある理由を考えることが子どもの自己肯定感につながります。
努力や結果を褒める
結果だけでなく努力の過程を具体的に褒めると、子どもの自己肯定感は高まります。自分の頑張りや工夫を認めてもらえると子どもは安心し、自分の価値を信じられるようになります。
子どもの自己肯定感を高めるための褒め方は以下のとおりです。
- 「すごい」「えらい」ではなく「最後まで諦めずに頑張ったね」と過程を伝える
- 「頭がいいね」ではなく「よく考えたね」「たくさん練習したね」と行動を褒める
- 「手伝ってくれてお母さんは嬉しいよ」のように自身の気持ちを伝える
子どもの行動に焦点を当てた言葉をかけることで、子どもの自己肯定感が育まれます。
他の子どもと比較しない

他の子どもと比較することは子どもの自己肯定感を傷つけてしまうため避けましょう。他人と比べられると、子どもは「ありのままの自分には価値がない」と受け取ってしまいます。すべての子どもにはそれぞれ成長のペースや個性、得意・不得意があります。
親として大切なことは他の子どもと比較するのではなく、子ども自身の成長を見守ることです。子どもの自己肯定感を高めるためには、比較の基準を「他の子ども」ではなく「過去の子ども」にしましょう。「前よりできるようになったね」と成長した点を認めることが、子どもの自己肯定感につながります。
失敗を成長の一部として捉える
子どもが何かに失敗した時は成長のチャンスとして捉えましょう。失敗した時に「なぜできなかったの?」と問い詰められると、子どもは挑戦を怖がるようになってしまいます。子どもの自己肯定感を高めるためには、失敗を責めるのではなく挑戦する心を育てる機会に変えることが欠かせません。
子どもが失敗を成長の一部として捉えられるように、以下の関わり方を意識しましょう。
- 「よく頑張ったね」と子どもが挑戦した勇気や努力の過程を褒める
- 「次はどうしたら上手くいくかな?」と子どもと一緒に考える
- 「悔しかったね」と子どもの気持ちに共感する
- 自身の失敗談を話し、子どもに安心感を与える
- 「失敗は新しいことを学ぶチャンスだよ」と子どもに伝える
失敗を前向きに受け止められる環境を整えることが、子どもの自己肯定感を高める土台となります。
毒親育ちでも自己肯定感は高められる

毒親に育てられた経験があっても自己肯定感は高められます。自己肯定感は生まれつきではなく、日々の考え方や行動で育てられるものです。自分を癒し大切にすることから始め、小さな成功体験を積み重ねていきましょう。
自分を肯定できるようになると、前向きな気持ちが子どもにも伝わります。自己肯定感を高めるために、まずは今日できたことを1つ見つけて自分で認めてみましょう。